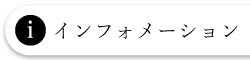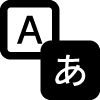美術館の歴史
- HOME
- >
- 美術館の歴史
歴史
大原美術館は、倉敷を基盤に幅広く活躍した事業家大原孫三郎が、前年死去した画家児島虎次郎を記念して1930(昭和5)年に設立した、日本で最初の西洋美術中心の私立美術館です。
日本美術のコレクターでもあった孫三郎は、友人でもあった虎次郎の才能と、美術に対する真摯な姿勢を高く評価し、三度にわたる渡欧を促します。虎次郎は、そこで制作に励むかたわら、孫三郎の同意のもと、日本人としての感覚を総動員してヨーロッパの美術作品を選び取るという作業に熱中しました。
明治の気骨を持つ虎次郎の選択は、東洋の感覚と西洋美術の精華との真剣勝負でした。彼は、エル・グレコ、ゴーギャン、モネ、マティス等、今も大原美術館の中核をなす作品を丁寧に選び、倉敷にもたらします。同時に進めた中国、エジプト美術の収集にも、東西の狭間で悩みつつ文化の源流に迫ろうとした虎次郎の心情が伺い知れます。
大原美術館は、その後も、倉敷の地にあって活発な活動を続け、西洋の近代から現代の美術、日本の近代から現代の美術、民芸運動にかかわった作家たちの仕事等にコレクションを広げ、日本人の心情に裏打ちされた独特の個性を発揮するユニークな民間総合美術館として世界に知られるようになりました。
今日、大原美術館は、現場で子供達や社会人を対象とした種々の教育普及活動に加え、毎夏の美術講座や、世界を代表する音楽家を迎えてのギャラリーコンサート等を通じ、諸芸術のフロンティアと広く関わりながら、21世紀に生きて躍動する美術館として、多彩な活動を展開しています。
あゆみ
| 1930(昭和5)年 | 11月5日完成。大原美術館が日本初の西洋美術中心の私立美術館として倉敷に誕生。 初代館長として武内潔真(たけうち きよみ)が就任。 |
|---|---|
| 1935(昭和10)年 | 3月 財団法人になる。初代理事長に武内潔真(たけうち きよみ)就任。 |
| 1943(昭和18)年 | 1月 創立者大原孫三郎逝去。 |
| 1946(昭和21)年 | 5月 第1回美術講座開催。 |
| 1950(昭和25)年 | 11月 創立20周年記念式および記念行事を挙行。 |
| 1951(昭和26)年 | 戦後初めての大規模展覧会開催。 6月 アンリ・マティス(Henri Matisse)展。 10月 パブロ・ピカソ(Pablo Ruiz Picasso)展。 |
| 1952(昭和27)年 | 4月 博物館法による登録美術館に認定。 |
| 1955(昭和30)年 | 11月 創立25周年記念式および記念行事を挙行。 |
| 1960(昭和35)年 | 11月 創立30周年記念式および記念行事を挙行。 |
| 1961(昭和36)年 |
5月 分館開館。 11月 陶器館開館。(現 工芸・東洋館 Craft Art and Asian Art Gallery) |
| 1963(昭和38)年 | 11月 芹沢銈介染色館、棟方志功版画館開館。(現 工芸・東洋館 Craft Art and Asian Art Gallery) |
| 1964(昭和39)年 | 4月 第2代館長として藤田慎一郎就任。 8月 第2代理事長に大原總一郎就任。 |
| 1965(昭和40)年 | 11月 創立35周年記念式および記念行事を挙行。 |
| 1968(昭和43)年 | 9月 第3代理事長に田中敦就任。 |
| 1970(昭和45)年 | 11月 創立40周年記念式および記念行事を挙行。 同月 東洋館開館。(現 工芸・東洋館 Craft Art and Asian Art Gallery) |
| 1972(昭和47)年 | 11月 倉敷アイビースクエア内に児島虎次郎室開室。 |
| 1980(昭和55)年 | 11月 創立50周年記念式および記念行事を挙行。 |
| 1982(昭和57)年 | 11月 第1回ギャラリーコンサート開催。 |
| 1990(平成2)年 | 11月 創立60周年記念式および記念行事を挙行。 |
| 1991(平成3)年 | 5月 第4代理事長に大原謙一郎就任。 9月 本館増改築工事完了。 |
| 1993(平成5)年 | 未就学児童対象プログラム事業開始。 |
| 1997(平成9)年 | 有隣荘(ゆうりんそう)特別公開開始。 |
| 1998(平成10)年 | 4月 第3代館長として小倉忠夫就任。 |
| 2000(平成12)年 | 11月 創立70周年記念式および記念行事を挙行。 |
| 2002(平成14)年 |
4月 第4代館長として高階秀爾就任。 8月 チルドレンズ・アート・ミュージアム開始。 ARKO(Artist in Residence Kurashiki, Ohara)開始。 |
| 2007(平成19)年 | AM倉敷(Artist Meets Kurashiki)開始。 |
| 2010(平成22)年 | 11月 創立80周年記念式および記念行事を挙行。 |
| 2011(平成23)年 | 6月 財団法人から公益財団法人へ移行。 |
| 2016(平成28)年 | 7月 第5代理事長に大原あかね就任。 |
| 2017(平成29)年 | 12月 倉敷アイビースクエア内の児島虎次郎室閉室。 |
| 2019(令和元)年 | 10月 中国銀行倉敷本町出張所跡に新児島館(仮称)暫定開館。 |
| 2020(令和2)年 | 11月 創立90周年記念フォーラム(オンライン)開催。 |
| 2022(令和4)年 | 新児島館(仮称)の正式名称が児島虎次郎記念館に決定。 |
| 2023(令和5)年 | 7月 第5代館長として三浦篤就任。 |
| 2024(令和6)年 | 4月 「公益財団法人大原芸術財団」へ財団名変更。 |
| 2025(令和7)年 | 4月 児島虎次郎記念館 グランドオープン |
大原孫三郎の業績
1902(明治35)年に、孫三郎が倉敷精思高等小学校の教室を借りて開いた学校です。そこで学んでいたのは、会社や工場、商店などで働いているため、昼間学校に通うことのできない人たちでした。学校は夜開かれ、生徒たちは商業や英語、数学、修身(今の道徳のようなもの)を中心に勉強しました。孫三郎自身は校長となり、修身を教えていました。なんと、23才という若い校長先生だったのです。倉敷の人たちに教育を受けさせようとする、孫三郎の熱心な気持ちが伝わるようです。
明治時代、多くの人たちは小学校を卒業すると働かなくてはなりませんでした。なかには、もっと勉強したいと願っている人もいましたが、十分な学費がないために諦めることが多かったのです。 孫三郎はそんな人たちを助け、勉強を続けることができるようにしました。この学費を捻出するために、多くの人に呼びかけてつくったのが倉敷奨学会です。そして孫三郎は、ただ学費を与えるだけでなく、励ましの手紙を同封したり、直接会って話をしたりするなど、若者たちが立派に成長するように心がけました。孫三郎の手助けで大学に進んだ人たちの多くは、その後、世の中で活躍しました。児島虎次郎もそのうちの一人です。
大原家は、500ヘクタール(東京ドーム、約107個分)の田畑を持ち、そこではなんと2500人もの小作人が働いていました。大原家のために働く小作人の姿を見て育った孫三郎は、早くから農業に関心をもっていました。
1914(大正3)年、孫三郎35才のとき、自分の土地で働く小作人たちだけでなく、田畑で働くすべての人の力になりたいと考え、農業研究所を設立ました。そこでは、種や肥料、害虫・病気などの研究が進められました。研究に役立つ本もたくさん集められ、図書館も建てられました。
岡山県の代表的な果物である桃や葡萄の新しい品種が、この研究所で生み出されたことは特に有名です。この研究所が、「果物王国」と呼ばれる岡山県のもとを作ったと言ってもよいでしょう。
(The Ohara Institute for Social Research,
Hosei University)-
この研究所は、1919(大正8)年に設立されました。そのころ世の中では、多くの人々が苦しい生活を送っていました。子どもたちの多くも生活を助けるため、小学校を卒業するとすぐに工場などに働きに出たり、家の仕事を手伝ったりしなければなりませんでした。「大原家の財産はすべて神のため、社会のために使われるべき」という考えをもっていた孫三郎が、この研究所の創設を思い立ったのは当然のことかもしれません。研究所では、どうすれば豊かな人々と貧しい人々の差がなくなり、みんなが幸せに暮らすことができるようになるか研究が進められました。